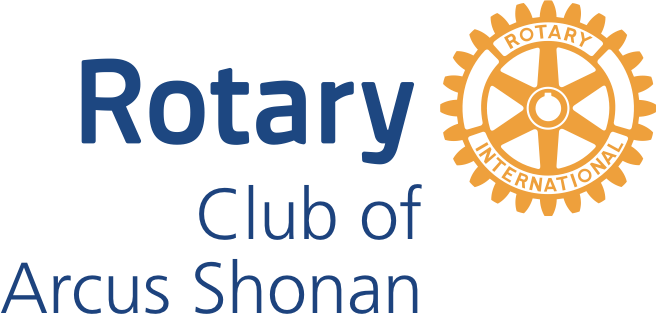第454回 例会2024年12月4日(水)0:00〜2024年12月10日(火)23:59 開催
開 会
点 鐘
国 歌
ロータリーソング
四つのテスト
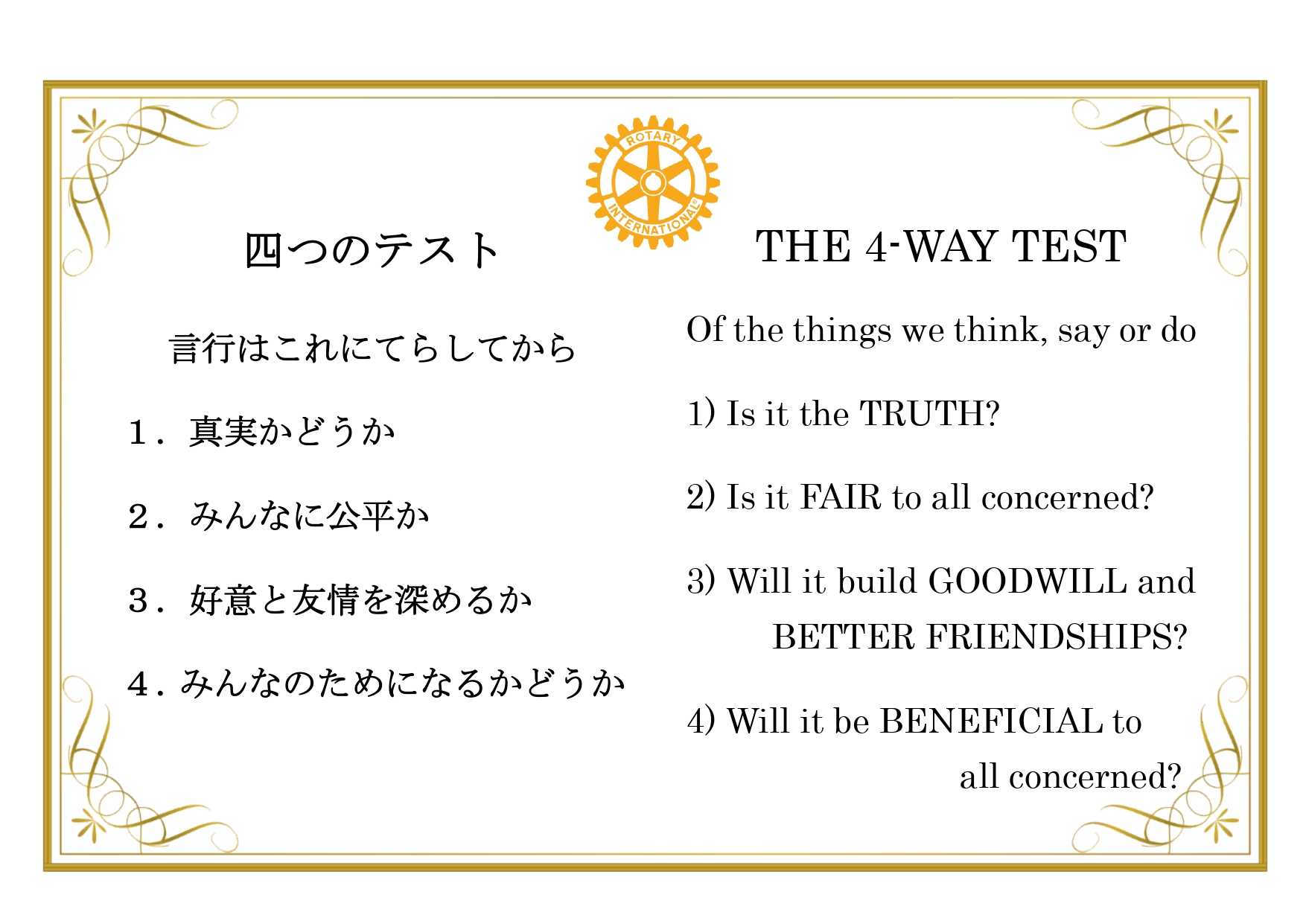
会長の時間
2024-2025年度会長 原 いづみ
皆さんこんにちは!第454回例会へようこそ!!
いよいよ12月、今年も残すところあと20数日となりました。師走はいつもにも増して何かとバタバタ忙しくなる時期で、さらにはあちこちの忘年会で毎日お付き合いが大変という方も多いのではないでしょうか。
12月というと、子供の頃は毎年父のクラブのクリスマスパーティ(クリスマス家族親睦会)を楽しみにしていたものでした。今でこそ会員数が減ったり子供を連れて参加される会員も少なくなったりで、昔のような盛大なパーティーは行われていませんが、○○年前とは敢えて書きませんが(笑)、子供の頃は、というか、子供だったので余計に華やかに思えたのかもしれません。ドレスアップしてホテルで開催されるパーティーに参加するなど滅多にあることでは無く、ビンゴ大会でどのような景品を当てられるか、そしてどのようなプレゼントをもらえるか、子供にとってはワクワク・ドキドキがいっぱいでした。 今思うと、こうしたある意味「きちんとした」場に連れて行かれて行っていたことでマナーや振る舞いといったところを自然と学び、クリスマスパーティーのみならずクラブの活動に参加させていただいていたことで自然とロータリーに馴染んでいったのでしょう。
当クラブでは残念ながらクリスマスパーティー開催の予定はありませんが、他クラブではどのようなパーティー、親睦会あるいは忘年会が行われるのか興味のあるところではあります。いくつかお誘いいただいているところもあるのですが、予定が合わずに参加出来ないのが残念です。
さて、今月は「疾病予防と治療月間」です。ロータリーで疾病予防というと真っ先に出てくるのはポリオだと思われますが、「『疾病』とは、身体的、精神的に健康ではない状態のこと。つまり、『病気』を表す言葉です。」ということで、私自身かれこれ2年半ほど足に問題を抱え、この一年、半年は難しい決断に迫られ、今正にその決断が下せずに参っているところです。こうやって書いてしまうと軽い印象になってしまいますが・・・。
かつて父がロータリー財団などの寄付の話をしているときに「寄付を受けるのでは無く、寄付が出来る方であることを有り難く思わなければいけない」と教えられたことがあります。今は私自身も会員となり、様々なところで活動するなかでその教えはしばしば教訓としてよぎるのですが、生きるか死ぬかの病では無いにせよ、身体に病気を抱え、精神的にも健康とは思えない状況となると、語弊が生じるであろう事を承知の上で書きますが、大きな障害を抱えるようになったりしたらというようなことを考えたり、そういう方たちを目の当たりにすると、支援される側ではなく支援する側でいられることの有難味を、身をもって感じています。勿論、世の中には障害を抱えながらもそれらを乗り越え、他者のために貢献されている方が沢山いらっしゃるのは理解しており、私なんぞはそうした方たちに比べたらほんの些細な問題なのかもしれませんが、五里霧中の中からなかなか抜け出せずにいる今日この頃です。皆さん、健康第一に!一度失うと二度と戻らないこともありますよ!!
幹事報告
2024-2025年度幹事 大塚 和光
◆財団室NEWS 2024年12月号◆
下記よりご覧ください。
【202412_TRF_News】
委員会報告
出席委員会
第453回例会 出席率 66.6%
会員数 3名 出席者 2名 欠席者 1名
Visitors
第453回例会のビジターコメント
広島北ロータリークラブ 村越 和也 様
ロータリー財団学友(Rotary Foundation Alumnus)という言葉は知っていましたが、学友のお話を聴く機会はありませんでした。ロータリー財団の奨学金プログラムやインターンシップ、ボランティア活動などに参加した人が学友であると定義されています。
ロータリー財団学友の意義は、個人および地域社会に対する影響力と持続的なつながりを持つことにあります。
田中克昌さんはイギリスでの活動、岡山夏生さんはフランスでの活動報告をしてくださり、日本の中にいては気付かない、海外から見た日本の現状を知ることができました。彼らの活動は、まさしくロータリー財団の理念と価値観を実践し、他のメンバーやコミュニティに影響を与えています。
これからも、ロータリーの価値観を共有する世界中の専門家やリーダーとつながり、ロータリーのプログラムやプロジェクトを通じてリーダーシップスキルを磨き、継続的に学び続け、新たな知識やスキルを身につけることでますますの活躍を期待しています。
この度はビデオレターという形ではありましたが、貴重な体験を知ることができ、ロータリー財団の活動をまた一つ勉強できました。私もこの度の例会に参加させていただき、新たなモチベーションが高まり、さらなる活動への意欲が湧きました。
Smile Box
第453回例会のスマイル報告
前回はありませんでした。
カレンダー
今週のプログラム
きものがたり歳時記(五十六)
卓話者:十一代目大塚重郎右衛門 様
外套
オーバー・オーバーコート・冬オーバー・冬コート。とんびは回套(まわし)・二重回しともいい、今はすたれた。マントは多く学生が用い、釣り鐘型なので釣鐘マントとも言う。婦人用の和装の上っ張りをコートと言い、東(あずま)コートはその変型。被布は羽織に似てオクミの深い外出着。婦人用の洋装の冬コートには、末広がりのフレヤーコートや、胸の形をとったシェープドコートやカクテルコート・イブニングコートその他種類が多い。短いものをトッパーコート、ウエストをしぼったものをボレロと言う。
外套の裏は緋なりき明治の雪 青邨
横町をふさいで来るよ外套(オーバ)着て 左右
美しき老刀自なりし被布艶に 虚子
外套のなかの生ま身が水をのむ 桂 信子
「女身」(1955)所収の句。三宅やよいさんが「増殖する俳句歳時記」の中で取り上げています。当時の作者を「厳しい寒さから身を守る厚手の外套は同時に柔らかな女の身体を無遠慮な世間の視線から守ってくれるもの。夫を病気で亡くし戦争で家を焼失したのち長らく職にあった信子にとって、女である自分を鎧っていないと押し潰されそうになる時もあったのではないか。」と慮ります。「口にした一杯の水の冷たさが外套の中の生ま身のからだの隅々にまでしみ通ってゆく。その感触は外套に包み隠した肉体の輪郭を呼び起こすようでもある。」「生ま身」とひらがなを余しての表記に外套からなまみの身体がのぞく痛さを感じさせる、として「彼女の俳句には緊張した日常の中でふっとほころびる女の心と身体が描かれていて、切なくなる時がある。」と。非常な、感覚的な句。
紙衣(かみこ)
白い厚紙に柿渋をぬり、幾度も日に干し露にさらし、足で踏み手で揉み、やわらかくして拵える衣服。紙子。紙ぎぬ。
帋子着てふくれありくや後影 召波
勿体なや祖師は紙子の九十年 句仏
ぶらさがる紙子を干すや秋の風
作者名がありませんが、最近の真夏は暑すぎるので残暑に入ってから虫干をしている、という句。古びた紙子を干しながら、渋味を塗り足すなり繕って次の冬も着るかそれとも買い換えるか、決めかねるうちに秋の風が吹いてきた。干されているのは紙子ではあるが古ぼけた己の姿をそこに重ねて眺めているのです。掲句の紙子は三冬の季語。虫干は晩夏の季語。土用の頃、衣類や古物などを風に干して虫を払い、土用干、虫払ともいう。梅干を干すのもこの頃。そして、秋の風。はて、掲句の季語は次のどれでしょうね。紙子、虫干、秋風。高浜虚子にも次の句があります。昔は物を大切に使った、使わざるを得なかったのです。
繕うて古き紙子を愛すかな 虚子
毛衣(けごろも)
毛皮製の防寒衣。犬・兎、高級品は狐・猟虎(らっこ)・栗鼠(りす)・羆(ひぐま)などを用いる。
裘(かわごろも)・皮衣(かわぎぬ)・孤裘(こきゅう)・革ジャンパー。
映画館裘匂ひ穢土なるや 誓子
犬の皮着てとつとつとはや失せぬ 青邨
毛衣にかくまで妻を老いしめき 康治
俳誌「谺」の山本一歩先生が「小林康治『虚実』の世界Ⅱ」に取り上げています。毛衣について、歳時記には狐、貂、栗鼠などの毛皮を使うのは高級品とあるが掲句の場合は粗末な袖無のようなものであったことだろう、とされます。そこで、普段は意識したことはなかったのだが、その粗末さの故か、いつになく妻が老いて見えた、のだと。「あの若かった愛妻をここまで年取らせてしまったか」という思い。時間は誰にでも平等に流れる。妻の老はそのまま我が老、言っても詮無いことだが、と。一歩主宰の師を見る眼差しが窺えます。
49号の「秋扇」について「秋扇のイメージを改めて認識させて頂きました」との感想をいただきました。それに加えて「座敷帚、懐かしいです。お茶殻などを撒いて掃き出していました。お茶の間の掃除は堀炬燵の布団を上げて掃いていました。」とも。座敷帚、お茶の間、堀炬燵。どれも懐かしい言葉になってしまいました。
我が家でも普段は茶殻を湿らせたものを使っていたと思いますが年末の大掃除の時は女中さんたちが古新聞を濡らして使っていましたね。お茶殻だけでは間に合わない。
掘り炬燵は畳半畳程の大きさがありましたから、秘密基地みたいにして妹たちと遊びました。その上の蛍光灯を点けたり消したりして「退避~っ」と言って潜り込むのです。まだ戦争の記憶が残っていた時代の遊びでした。
※引用文は山本健吉編【季寄せ】(昭和四十八年文藝春秋社刊)による。
※本稿は阿夫利嶺俳句会の月刊誌「阿夫利嶺」に掲載されている連載を編集して掲載しております。※
閉 会
点 鐘